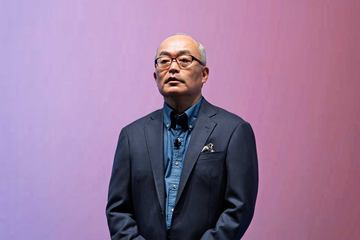西田宗千佳のイマトミライ
第278回
ソニー=エレクトロニクスは遠い過去に ソニーグループの今とトップ交代
2025年2月3日 08:20
ソニーグループは、取締役代表執行役社長CEOに十時裕樹氏を据えることをはじめとした組織改編を発表した。
発表された内容自体には大きなサプライズはなく、ソニーグループの運営自体が計画的に「十時時代」へと移行しつつあることを感じさせるものだった。
とはいえ、多くの人にはそれがなにかちょっと分かりづらいかもしれない。
そこで今回は、今のソニーグループがどんな体制にあり、どんな企業になろうとしているのかを解説してみたい。
10年のあいだに起きたソニーの変化とは
15年前、ソニー(現ソニーグループ)の業績は伸び悩んでいた。そこに変化が産まれ、構造変化が可視化されてきたのは、2015年頃かと思う。
この10年での変化は、3名のトップによって成し遂げられてきた。1人目は2012年にCEOに就任した平井一夫氏であり、2人目は2018年からCEOとなった吉田憲一郎氏であり、そして、3人目が現CEOの十時裕樹氏である。
平井体制となるときに吉田氏がCFOとなり、十時氏が業務執行役員として、ソニーモバイルコミュニケーションズからソニー本社に戻ってきた。平井氏による変革を吉田氏と十時氏が支え、さらに吉田氏の路線を十時氏が継承して変化させていく……という流れがあると考えればいい。
3世代のトップが行なってきたことはなにか?
それは、ソニー=エレクトロニクスという体制の見直しであり、ソニーの中にあって収益を上げていたゲーム・映画・音楽という部門とのつながりを再構築することだ。
現在のソニーグループは、ゲーム・映画・音楽・ET&S(エンタテインメント・テクノロジー&サービス)・半導体・金融の6分野で成り立っており、「ソニー」は旧エレクトロニクス事業であるET&Sを担当する企業の名前になっている。
このことを「エレキの縮小」とみるのは簡単だ。
他方で、過去と同じように家電事業をできている企業は非常に少ない。
パナソニック(松下)や日立は業態を大きく変えた。
パナソニックは今年のCESで基調講演をしたが、家電製品の話はほとんど出てこなかった。電池を軸にしたビジネスと、AIを軸にした事業の話が中心だ。
その前、2013年にパナソニックが基調講演に登場した時にはテレビやタブレットの話が中心であったのとは好対照である。
東芝も家電事業を手放した。テレビ事業のレグザはHisense傘下で好調ではある。シャープも鴻海傘下となり、事業再構築が進んでいる。
韓国系のサムスンやLGはまだ大きな規模を維持しているが、個々の製品では中国系の猛追を受けている。サムスンはスマートフォンがあるので「個人向け」として元気な状況にあるが、家電メーカーの姿としては「例外的にうまくいっている」と言えるかもしれない。
世界的に見ても、「家電メーカー」のほとんどは2000年代から2020年代への変化に耐えきれなかった。それを残念と思う気持ちもあるが、なにも日本だけの問題ではない。製造のエコシステムとスマホを中心としたビジネスエコシステム、この両方の変化の中では、家電からよりも別の軸から伸びる企業の方が有利であった、ということだろう。
各社はその中で色々な生き残り策を模索した。
もともと持っている開発力や企業体力を活かして「企業向けのビジネス」を指向するのも1つの策ではある。
それと同時に、「コンテンツとそれを生み出すエコシステム」に普遍性を見いだし、価値拡大を図ったのがソニー、ということができるだろう。
十時氏はそれを昨年の経営方針説明会では「Creative Entertainment Vision」というキーワードで説明している。そのキーワードは現在も健在だ。
「グループ間のつながり」を強調する十時体制
平井氏時代にはコンテンツ自体の価値がアピールされ、吉田氏時代には「コンテンツを作るための環境としてのエレクトロニクス」にもフォーカスが当たった。十時氏はその体制を維持するものの、さらに「横のつながり」を意識した事業展開になると予想される。
例えば今回のCESでのプレスカンファレンスでは、アニメや映画に関しても「グループをまたいだ連携」がアピールされた。日本のソニー・ミュージックエンタテインメント傘下のアニプレックスと、ソニー・ピクチャーズエンタテインメント傘下であるCrunchyrollが共同でアニメをアピールし、ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)のゲームIPが前述2社の協力でアニメ化され、SIEのゲームIPがさらに映画・ドラマになる。
そういう事例を集めただけ……という冷めた見方もできるが、それらの連携でちゃんと「収益のあがるヒット作品」が産まれ、ソニーグループを象徴するものになっている。
ブースに展示された「PXO AKIRA」もそうだ。これは、ソニーグループが2022年に買収したドイツのVFX企業・Pixomondoが作ったシステム。自動車などを稼働する台の上に乗せ、背景のディスプレイに表示されるCGとともに撮影するバーチャルプロダクション・システム。自動車を屋外に持ち出す事なく、走行イメージの撮影ができる。
ソニーグループのある人物は、「過去のような判断なら、ソニー・ピクチャーズも買収に至らなかっただろう」と話す。
なぜなら映画のためだけなら、買収せずに事業協力でもいい。
だがこの技術はもっと幅広く使える。
例えば現在、自動車会社との商談が進んでいるという。CM撮影を社内で完結できるのも大きいが、開発途上の車について社内共有用の資料を作る場合でも、車外に車を出さず、機密を守りつつ作業できることが評価されているという。
このように、「映画にも使えるが他の産業にも使える」という横断的な発想を進めるのが、十時体制が狙うものでもある。
それがどこまでできるかはわからないが、「横断的発想」が社内から自発的に出てくるように企業風土を整備し、グループ内で使える武器を増やすために積極投資していく流れであるのは間違いない。
十時氏はそうした「投資判断」こそが持ち味だ。
実は、ソニー・ホンダモビリティでの自動車作りについても強く後押ししたのは十時氏と言われている。
SIEは西野氏がCEOに
今回の組織改編では、ソニーグループの軸となる2つの会社についてもトップ変更が合った。
SIEでは4月1日付けで、西野秀明氏が社長CEOに就任する人事が発表された。
西野氏はSIEでプラットッフォーム開発の責任者を長く勤めており、現在はプラットフォームビジネスグループCEOである。
SIEは2024年3月にジム・ライアン氏がCEOを退任後、十時氏が暫定的にCEOを務めた。その後、2024年6月に十時氏が会長に就任、プラットフォームビジネスグループを西野氏が、スタジオビジネスグループをハーマン・ハルスト氏がCEOとして統括する「2トップ体制」だった。それが今回、スタジオビジネスグループCEOをハルスト氏が務める体制のまま、会社としてのトップは西野氏が務める形へと変化した。
企業としての舵取りを一本化する、という狙いが強いと思われるが、プラットフォームとスタジオの考え方自体に大きな変化ないと思われる。
現状では世界的にゲームビジネス自体の退潮が伝えられており、コスト面の課題も大きい。次にインタビューの機会ができたら、そうした部分の方針を聞いてみたいと思っている。
半導体事業も若返りへ
ソニーグループのもう1つの柱である半導体事業を司る、ソニー・セミコンダクタソリューションズにも変化があった。
4月1日付けで、2000年代以降ソニーで半導体事業を長く率いてきた清水照士氏が社長兼CEOから取締役会長となり、指田慎二氏が代表取締役兼社長CEOになる人事が発表された。
指田氏はスマートフォン向けのイメージセンサー事業を率いてきた人物で、ソニー・セミコンダクタソリューションズの記者向け説明会などでも、清水氏にかわりスマートフォン向け事業の質疑に立つことも多かった。同社の収益がスマートフォン向けに支えられている現状では、妥当な人事と言える。
筆者が注目したいのは、新たに同社執行役CTOに、第1研究部門長だった大池祐輔氏が、研究開発センター長を兼務する形で就任したことだ。
大池氏はほとんどメディアに出てきたことがないため、知らない方が多いのではないだろうか。同社の研究部門の主軸であり、将来の方向性を舵取りする人物でもある。
以前に大池氏と「未来のイメージセンサー」について議論させていただいていただいたことがあるが、非常に刺激的な取材だったのを覚えている。
半導体事業は一般的な事業に比べ、研究から製造、市場への投入までの期間が長い。研究は10年がかりだと言うし、半導体工場が立ち上がるにも、計画開始から6年近くを必要とする。
長期視点での開発と戦略が必須であり、難しい事業であるのは間違いない。
世界的にも、そうした先端的な技術開発ができている半導体企業の数は少ない。日本ではほんの数社といったところだろうか。
今後もソニーの半導体事業が「先端」を維持するには、新しい経営陣の力が必須である。